法人が保有する仮想通貨については、平成31年度(令和元年度)の税制改正により、税務上の取り扱いが明確化されました。
この記事では、法人における仮想通貨の時価評価について記載しています。
個人の所得税における取り扱いは法人とは異なりますが、この記事では対象外です。
活発な市場が存在する仮想通貨は時価評価が必要
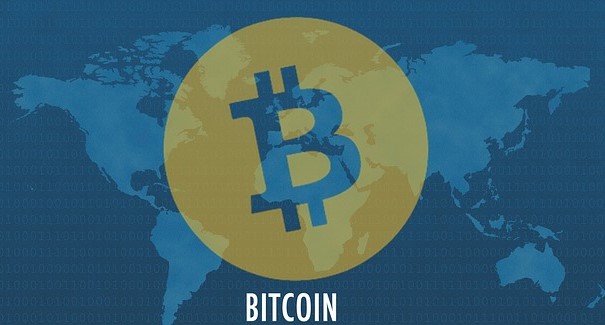
平成31年度(令和元年度)の税制改正により、法人が事業年度末時点で保有している仮想通貨について、活発な市場が存在する場合には、時価評価を行うことが必要となりました。
したがって、期末の時価が上がっていれば評価益が計上され、逆に時価が下がっていれば評価損が計上されます。
評価益は税金計算上も益金に算入され、評価損は損金となりますので、年度末に法人が仮想通貨を保有している場合は、たとえ決済(譲渡や売却など)をしていなくても、評価損益(含み損益)によって税金の額に影響を与えることになります。
仮想通貨の時価評価が必要とされた背景
この改正が行われた背景としては、企業会計において時価評価を原則としていることもあり、活発な市場が存在するのであれば容易に売却や換金ができるため、年度末時点の評価損益を所得の計算に入れるほうが実態を適切に表すという理由があります。
また、仮想通貨以外の本業の所得が多額に出そうな事業年度に、含み損のある仮想通貨だけを売却して、本業の利益と相殺させる行為が想定されてしまうことなども、改正の背景として挙げられています。
活発な市場が存在しない場合
上記の通り、時価評価が必要になるのは「活発な市場が存在する仮想通貨の場合」と定められています。
そのため、保有している仮想通貨に活発な市場が存在しない場合、税務上は、時価評価を行う必要はありません。
その場合、購入した時の価額のまま据え置かれることになります。
評価額の下落を反映させる「低価法」のような処理を行う必要はない、ということです。
活発な市場が存在するかどうかで処理が分かれる
ここまでをまとめると、税務上の処理については、活発な市場が存在するかどうかで処理が分かれることになります。
- 活発な市場が存在する仮想通貨 → 時価法
- 活発な市場が存在しない仮想通貨 → 原価法
会計上の処理と税務上の処理の違い
ここまでは、税務上の取り扱いをまとめましたが、会計上の取り扱いとの違いも確認しておきます。
会計と税務に違いがあるのは活発な市場が存在しない場合
会計上と税務上の処理に違いがあるのは、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合の評価方法です。
会計上、活発な市場が存在しない場合には、「切放し低価法」によることと定められていますが、税務上はこの方法は採用されていませんので、あくまで原価法を採用することになります。
適用は2019年4月1日以後終了年度から
上記の税制改正によって時価評価が必要となるのは、2019年4月1日以後に終了する事業年度からが原則となります。
したがって、早い企業だと、2018年5月から2019年4月を1事業年度としている法人等が該当します。
ただし、この適用には経過措置が設けられており、「2019年4月1日以前に開始し、同日以後に終了する事業年度」については、期末時点で保有している仮想通貨を会計上時価評価していないときは、税務上も時価評価しなくてもよいという取り扱いが定められています。
ちなみに、この経過措置期間に該当する事業年度において、会計上時価評価していない場合に、あえて税務上だけ時価評価することは可能です。
この場合は、会計上の決算書には仮想通貨の時価評価損益が計上されていませんので、税金計算を行う際に申告調整によって税金計算に反映させます。
つまり、会計上、時価評価を行った場合は税務上も評価損益を計上する方法しかありませんが、その逆で、会計上、時価評価を行っていないときに、税務上、時価評価するかどうかは、選択の余地があるということです。
2019年4月1日をまたぐ事業年度の取り扱いをまとめると、次のようになります。
- 会計上、時価評価を行った → 税務上も時価評価を行う
- 会計上、時価評価を行っていない → 税務上も時価評価しなくてよいが、あえて税務上だけ時価評価することも妨げられていない
まとめ
平成31年度(令和元年度)の税制改正により、法人が期末日に保有している仮想通貨について、活発な市場が存在する場合には、時価評価を行うことになりました。
譲渡等せずに保有しているだけのタイミングでも税金の額に影響を与えますので、法人で仮想通貨の取引を行う場合は、期末日の時価に留意する必要があります。